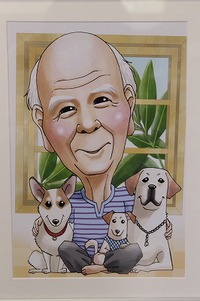2012年06月08日
「真壁ちなー」に伝わるジーファー
触れるとひんやりと冷たく、
堅いはずの金属なのに、なにかこうとろけるようでもあり。
艶やかで、なめらかで。
手にとれば、目でみるよりもぐっとほっそりと感じられ、
なんて華奢なのだろうと・・・。
ああ、町の女たちが常日頃その髪にさしていた簪は、
こんなにも軽やかで清らかであったのだと驚かされました。

糸満の、海から離れた真壁という集落のなかに、
明治24年頃に建てられた古民家(有形文化財)で営まれているお茶処があります。
おいしい沖縄そばや、チャンプルー、ぜんざいなどをだす店です。
店の名は、「茶処 真壁ちなー」。
お店を囲む白い石垣は、身長160㎝ある私よりもずっと高く、
そしてたっぷりとした厚みのあるたいそう立派なものでした。

石畳に誘われ門からはいれば、
そこには赤瓦をのせた立派な木造の民家が。

↑・石垣、ワーフール、そして家屋が有形文化財は指定
その風景の、心地いいこと。
緑豊かな庭、水色の空、赤い屋根に、
屋敷へと誘う灰白色の石畳、
そして木の家と、それをしっかと支える柱と基礎となる石積み。
こちらの屋敷は、家全体が、石で造られた台座のうえにあるのです。
激しく雨が降る日、蒸し暑い日・・・。
この家はいつも涼やかで、健やかに暮らせる空間であったろうなと。
そうして、冒頭でご紹介したジ-ファーは、
この気持ちの良い住まいで暮らしていた“金城ウシさん”のもの、と思われるのです。
ウシさんは明治33年のお生まれで、
昭和50年にお亡くなりになりました。

先の簪を見つけたのは、「茶処 真壁ちなー」を始めるにあたり、
ウシさんのお孫さんのお嫁さん、である金城正子さんが、
この屋敷の片づけをなさっていたときのこと。
いまから13年前のことだそうです。
正子さんが、
ものがいっぱい詰まっていたという食器棚を片づけていたときに、
このなかから2本の簪をみつけのです。
男性用の簪が1本、女性用が1本。
ながいあいだ棚に仕舞われたままだったその簪たちは、
真っ黒だったそうです。

「父にあったような気がした」
又吉健次郎さんは、この簪に触れたときのことを、こうあらわしました。
出会いは、男簪のうちの1本の頭が、ぐらぐらしていたから直してもらえるかも、
と、正子さんが「金細工またよし」の工房を訪ねてきてくれたとき。
2本うちの1本、
女性用のジーファーが、
又吉誠睦氏の手になるものだったのです。
それは、誠睦氏の息子である健次郎氏には、一目瞭然でした。
この家で暮らしておられたウシさん。
そして、ウシさんが暮らしておられたその家から見つかった、ジーファー。
誠睦氏の手になるこのジーファーは、
いつ、どのようにして、どのような思い出とともに、ここにやってきたのか。

残念ながら、ウシさんがその髪にこのジーファーをさしていた、という記憶がある方は、
いないのだそうです。
明治生まれのウシさんと、
「茶処 真壁ちなー」を切り盛りしていらっしゃる昭和生まれの正子さんとがその人生を重ねあわしたのは、
正子さんが嫁いでこられた昭和47年から、ウシさんが亡くなれるまでの約3年間なのです。
しかもそのうちの半分ほどは、
正子さんはご主人の転勤にともない県外にいらしたので、
実際には1年半くらいなのです。
くわえて沖縄でのお住まいも、真壁と那覇と、別々だったので、
ウシさんに会われたのは、結婚の挨拶だったり、長女の誕生のお祝だったりの節目節目で、
決して回が多かったわけではなかったそうです。
それでも正子さんのなかに、ウシさんの思い出は刻まれていて、
でかけるときにはワンピースを着ていたこと、
一方で、家で過ごすときには琉装なさっていたこと、
そして髪を結いあげていたことも覚えていらっしゃるのです。

この写真は、ウシさんが着ていたと思われる芭蕉の着物です。
バザーと呼ばれる野良着。
仕事着だから、裾は短め。
胸元の裏側には、白い布でポケットが作られていました。
使いやすく、工夫なさったのでしょう。
そうゆうウシさんですから、
きっと、ジーファーをさしてらっしゃただろうと思うのです。
そして、もうひとつ。
糸満の真壁にお住まいだったウシさんなのですが、
ご主人の通勤を楽にしようと、
那覇の泉崎で家を買い、暮らしていた時代があったとのことなのです。
じつは、
いまは首里の石嶺町にある「金細工またよし」ですが、
戦前から、おそらく大正8年(誠睦氏19歳)頃あたりから、
昭和19年に那覇の街を焼き尽くした“十・十空襲”まで、
工房は、那覇の、現在の泉崎にあったのです。
左の写真が、その頃の工房を守っていた6代目又吉誠睦氏です。
とすると、戦前、
金城ウシさんという女性が泉崎で暮らし、
又吉誠睦氏という金細工職人もまた泉崎で仕事をしていたと、
ふたりの時間が泉崎で交錯するのです。
もしかしたら、このときにウシさんは、
誠睦氏からジーファーを買い求めたのかもと。
幸せな想像は、膨らむばかりなのです。
食器棚の奥からでてきた、すっかり黒く変色していた、
使い手も作り手もともに明治生まれの方々というこの簪が、
平成を生きる正子さんのお手元に残っていること。
それはきっと明治に建てられ、
あの大戦と戦後を乗り越えた建物を、
その修復に私財を投じ、
クサビを使うなどの安易な方法でなく、
昔ながらのかたちを選び補修し、いまこうして多くの方々にみてもらう、
そうゆう風に使っていらっしゃる正子さんだからこそ、
起きたできごと、だと思うのです。
ありがたいことです。
大事に守り伝えてくださり、
本当にありがとうございます。
あの世でこのジーファーを打った誠睦氏が、
きっと微笑んでいることと思います。
↑・柱には戦時の弾痕が残っています。

*「茶処 真壁ちなー」(糸満市真壁)の公式ブログはこちらです。
お店の営業時間やアクセスなどの情報も掲載されています。
↓
真壁ちなーの日々(http://makabechina.ti-da.net/)
↓ ★ お店では、営業時のみ簪を展示してくださっています。おいしいお食事とスイーツをいただき、古民家でくつろぎ、ぜひ、簪もご覧になってみてください。


また、おそば食べに行きま~す♪
堅いはずの金属なのに、なにかこうとろけるようでもあり。
艶やかで、なめらかで。
手にとれば、目でみるよりもぐっとほっそりと感じられ、
なんて華奢なのだろうと・・・。
ああ、町の女たちが常日頃その髪にさしていた簪は、
こんなにも軽やかで清らかであったのだと驚かされました。
糸満の、海から離れた真壁という集落のなかに、
明治24年頃に建てられた古民家(有形文化財)で営まれているお茶処があります。
おいしい沖縄そばや、チャンプルー、ぜんざいなどをだす店です。
店の名は、「茶処 真壁ちなー」。
お店を囲む白い石垣は、身長160㎝ある私よりもずっと高く、
そしてたっぷりとした厚みのあるたいそう立派なものでした。
石畳に誘われ門からはいれば、
そこには赤瓦をのせた立派な木造の民家が。
↑・石垣、ワーフール、そして家屋が有形文化財は指定
その風景の、心地いいこと。
緑豊かな庭、水色の空、赤い屋根に、
屋敷へと誘う灰白色の石畳、
そして木の家と、それをしっかと支える柱と基礎となる石積み。
こちらの屋敷は、家全体が、石で造られた台座のうえにあるのです。
激しく雨が降る日、蒸し暑い日・・・。
この家はいつも涼やかで、健やかに暮らせる空間であったろうなと。
そうして、冒頭でご紹介したジ-ファーは、
この気持ちの良い住まいで暮らしていた“金城ウシさん”のもの、と思われるのです。
ウシさんは明治33年のお生まれで、
昭和50年にお亡くなりになりました。
先の簪を見つけたのは、「茶処 真壁ちなー」を始めるにあたり、
ウシさんのお孫さんのお嫁さん、である金城正子さんが、
この屋敷の片づけをなさっていたときのこと。
いまから13年前のことだそうです。
正子さんが、
ものがいっぱい詰まっていたという食器棚を片づけていたときに、
このなかから2本の簪をみつけのです。
男性用の簪が1本、女性用が1本。
ながいあいだ棚に仕舞われたままだったその簪たちは、
真っ黒だったそうです。
「父にあったような気がした」
又吉健次郎さんは、この簪に触れたときのことを、こうあらわしました。
出会いは、男簪のうちの1本の頭が、ぐらぐらしていたから直してもらえるかも、
と、正子さんが「金細工またよし」の工房を訪ねてきてくれたとき。
2本うちの1本、
女性用のジーファーが、
又吉誠睦氏の手になるものだったのです。
それは、誠睦氏の息子である健次郎氏には、一目瞭然でした。
この家で暮らしておられたウシさん。
そして、ウシさんが暮らしておられたその家から見つかった、ジーファー。
誠睦氏の手になるこのジーファーは、
いつ、どのようにして、どのような思い出とともに、ここにやってきたのか。
残念ながら、ウシさんがその髪にこのジーファーをさしていた、という記憶がある方は、
いないのだそうです。
明治生まれのウシさんと、
「茶処 真壁ちなー」を切り盛りしていらっしゃる昭和生まれの正子さんとがその人生を重ねあわしたのは、
正子さんが嫁いでこられた昭和47年から、ウシさんが亡くなれるまでの約3年間なのです。
しかもそのうちの半分ほどは、
正子さんはご主人の転勤にともない県外にいらしたので、
実際には1年半くらいなのです。
くわえて沖縄でのお住まいも、真壁と那覇と、別々だったので、
ウシさんに会われたのは、結婚の挨拶だったり、長女の誕生のお祝だったりの節目節目で、
決して回が多かったわけではなかったそうです。
それでも正子さんのなかに、ウシさんの思い出は刻まれていて、
でかけるときにはワンピースを着ていたこと、
一方で、家で過ごすときには琉装なさっていたこと、
そして髪を結いあげていたことも覚えていらっしゃるのです。
この写真は、ウシさんが着ていたと思われる芭蕉の着物です。
バザーと呼ばれる野良着。
仕事着だから、裾は短め。
胸元の裏側には、白い布でポケットが作られていました。
使いやすく、工夫なさったのでしょう。
そうゆうウシさんですから、
きっと、ジーファーをさしてらっしゃただろうと思うのです。
そして、もうひとつ。
糸満の真壁にお住まいだったウシさんなのですが、
ご主人の通勤を楽にしようと、
那覇の泉崎で家を買い、暮らしていた時代があったとのことなのです。
じつは、
いまは首里の石嶺町にある「金細工またよし」ですが、
戦前から、おそらく大正8年(誠睦氏19歳)頃あたりから、
昭和19年に那覇の街を焼き尽くした“十・十空襲”まで、
工房は、那覇の、現在の泉崎にあったのです。
左の写真が、その頃の工房を守っていた6代目又吉誠睦氏です。
とすると、戦前、
金城ウシさんという女性が泉崎で暮らし、
又吉誠睦氏という金細工職人もまた泉崎で仕事をしていたと、
ふたりの時間が泉崎で交錯するのです。
もしかしたら、このときにウシさんは、
誠睦氏からジーファーを買い求めたのかもと。
幸せな想像は、膨らむばかりなのです。
食器棚の奥からでてきた、すっかり黒く変色していた、
使い手も作り手もともに明治生まれの方々というこの簪が、
平成を生きる正子さんのお手元に残っていること。
それはきっと明治に建てられ、
あの大戦と戦後を乗り越えた建物を、
その修復に私財を投じ、
クサビを使うなどの安易な方法でなく、
昔ながらのかたちを選び補修し、いまこうして多くの方々にみてもらう、
そうゆう風に使っていらっしゃる正子さんだからこそ、
起きたできごと、だと思うのです。
ありがたいことです。
大事に守り伝えてくださり、
本当にありがとうございます。
あの世でこのジーファーを打った誠睦氏が、
きっと微笑んでいることと思います。
↑・柱には戦時の弾痕が残っています。
*「茶処 真壁ちなー」(糸満市真壁)の公式ブログはこちらです。
お店の営業時間やアクセスなどの情報も掲載されています。
↓
真壁ちなーの日々(http://makabechina.ti-da.net/)
↓ ★ お店では、営業時のみ簪を展示してくださっています。おいしいお食事とスイーツをいただき、古民家でくつろぎ、ぜひ、簪もご覧になってみてください。
また、おそば食べに行きま~す♪
Posted by 風音 at 14:16│Comments(2)
│お客様との縁
この記事へのコメント
時を超えての父君との出会い。素敵ですね。
昔のうちなーはどんなだったのだろう?としばし目を瞑りました。
注文させていただいた房の腕飾り、楽しみに待っています。
それが届けば42房です♫
昔のうちなーはどんなだったのだろう?としばし目を瞑りました。
注文させていただいた房の腕飾り、楽しみに待っています。
それが届けば42房です♫
Posted by はべRu at 2012年06月25日 15:23
at 2012年06月25日 15:23
 at 2012年06月25日 15:23
at 2012年06月25日 15:23ハイタイ
がんじゅぅさ そーいびーみ
楽しみにしていた指環と腕環、届きました!
すてきなお守りを作ってくぃみそーち、しでぃがふーでーびる!
がんじゅぅさ そーいびーみ
楽しみにしていた指環と腕環、届きました!
すてきなお守りを作ってくぃみそーち、しでぃがふーでーびる!
Posted by はべRu at 2012年07月03日 17:09
at 2012年07月03日 17:09
 at 2012年07月03日 17:09
at 2012年07月03日 17:09